映画『名もなく貧しく美しく』を観た
昭和の大女優、高峰秀子さんは昨年末に亡くなった。
その美しさは勿論なのだが、何か陰のある、不幸を背負ったような役柄、演技に惹かれていた。
最初に彼女の映画を見たのは大学生だったのだが、あまりよく理解はできなかった。しかし40代になって、人生の半ばを迎え、若いときに感じることができなかったことが徐々に理解できるようになって来たような気がする。
今では彼女の人生そのものが昭和であり、彼女の涙は昭和の日本女性の涙なのだ、と思う。
今作品は観たことがなかったのだが、たまたまNHK-BSでやっていたので観ることができた。
時は終戦前の空襲で始まり、戦後を迎える。高峰秀子演ずるろうの秋子が、同じろうの片山道夫(小林佳樹)と結婚し、日々の生活を過ごすために働くこと、また、生まれた子どもを育てることに苦難の連続を味わわせられながら、戦後の日本を生きてゆくストーリーである。日本でろう者を正面から取り上げた初めての映画であるようだ。
まず今、我々がこの映画を観て思うのは、戦後の日本(東京)の生活ぶりが分かるということ。当時有楽町のガード付近には靴磨きがズラリと並び、その多くはろう者であったそうだ。松山善三監督は映画化にあたり、50人ものろう者に手紙を出し、その返事から苦悩を読み取りシナリオに取り入れている。
※1961年東宝作品
2人がろう学校の同窓会で出会い、交際を経て結婚に至るとき、そして、内職用のミシンを弟に奪われて絶望し、弟ともども一緒に死のうと思いつめた秋子を追ったときの二度、秋子に向けて道夫が強く説く──「僕たちは特別なのだから、2人で助け合って、普通の人に負けないようにがんばらないといけません」。この、「普通の人に負けないように」というセリフ、この映画のポイントであり、当時のろう者もきっと強く共感し、大いに励まされたことだろう。そして電車の窓越しの手話での会話シーンは日本映画史上に残る名シーンだと思う。『私たちはお互いが助け合って生きていこう、と約束したことを忘れたのですか?』と問いかける場面では涙が…
1人目の子どもは耳が聞こえない故に異変に気づかず亡くしてしまう。2人に生まれた子どもの一郎が成長してゆく後半から、俄然と面白くなる。 ろうの両親を最初は疎ましく思い、避け、拒絶さえしていた一郎が、やがて、変わってゆく。(ろうの両親を持つゆえ)これまでは友達とけんかばかりしていた、「たまには友達を連れて来なさい」と言っても決してそうしなかった一郎が、あるとき友達を家に連れて来ている。初めてのことに、秋子は家に帰って一郎の友達の姿を見るや、即座に逃げ出してしまう。「私なんかがいたら恥ずかしいでしょう」。一郎を気遣ったつもりの秋子に、「紹介しようと思って連れて来たんだ」と、親を受け入れ、素直になった一郎の成長を示すシーン。
ろう者を親に持つ家庭で必ずある、よくあることだときく。また、ラストシーンで一郎に語らせる──「以前、僕は、両親がろうあ者なのを恥ずかしく思っていましたが、今ではちっともそう思いません。今はお父さんとお母さんを一番尊敬しています」と。それまでが徹底的に生意気で嫌な、秋子を不憫に思わせる子どもとして設定されていた分、観る者の心をなごませて微笑ましい。
物心ついた一郎が、社会の中でろうの両親の置かれている状況、両親の苦労に気付いてゆく、そのシーンが印象的だった。
洋服の仕立てを内職とする秋子に、「母さんはだまされている。ろうだから利用されているんだ」「母さんが働けば働くほど洋服屋が儲かる。いつも母さんは損ばかりしている」と。そして、「母さんの腕はいいですか?」「母さんがいなくなったら困りますか?」「仕立て代、他ではもっと高いです」と洋服屋にも正面からはむかう。
これは私自身も子どもの頃から(今でも時々)思うことが多い。家族をはじめ周りの人間に対しどうしてもっとうまく、ラクして要領よく生きてゆけないのか、と苛立たしく思えたことも多々あったのだ。
でも、社会はそういうものなのだと今では思う。世の中には世渡りのうまいものとそうでない者とがいて、その差は歴然としている。愚鈍な者はだまされ、要領が悪いようにできている。けれども、それと幸せとはまた別のことなのだということがよくわかる。
秋子の母は、家を出てバーでマダムとして働き、中国人の妾となり「お金が全て」という姉・信子に会ってつぶやく。「世の中は二人でも生きていけない人間と、一人で気ままに生きてる人間がいるんだね」。そしてまた、憤慨する一郎には笑顔で穏やかに諭す──「いいじゃないか。それでも、こうしてご飯が食べられれば」と。道夫もまた別に秋子に言う──「僕たちは十年かかってやっと一人前の夫婦になった」「耳がきこえないから、神様が倖せにしてくれたのかもしれません」。
自分がろうであることに苦しみ、子育てに自信が持てずに苦しみながら生きてゆく秋子が、母と道夫のやさしくあたたかい思いの中でなだめ励まされてゆく。道夫や母のことばには、この世を生きてゆく上での哲学的な箴言が含まれている、と思う。
まさにタイトルどおり、「名もなく貧しく」とも「美しい」生き方であると共感を覚えた。今観ても決して色褪せない、むしろ家族の絆、人間の絆が失われている今、現代を生きる我々が観ることにこそ、大きな価値のある映画であると思う。
それにしても、この時代の日本映画は素晴らしい、と心底思う。
自分の世代も含め若い世代はこんな映画があったこともほとんど知らない。
常々思っていることなのだが長い歴史と伝統、文化を誇る国の中で日本ほど『世代の断絶』が起きている国はない。
『今は昔と違う』『価値観が変わった』『今時そんなこと…』年配者からの諫言に対して日本の若者からよく出る言葉だ。そう返されるのがわかっているから今は誰も何も言わない。そうして日本社会は変容してきている。
しかし『日本人としての美徳』や『道徳心』『公共心』などは時代は変われども不変のものなのではないか。
観賞後そんなことを強く感じたのだった。








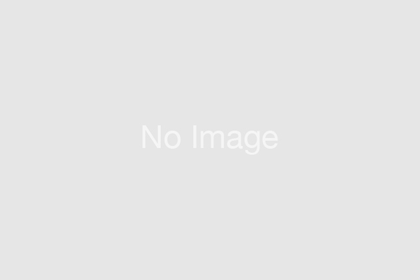



コメントを残す